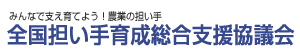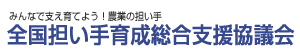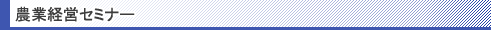
Ⅱ.税金講座
税理士 秋葉芳秀
1.本来は厳しい家事関連費
個人農家の場合、支出する費用によっては家計分と事業分が一緒になる家事関連費と呼ぶものが多い。この場合の記帳方法、決算整理の仕方、領収書等のもらい方及び整理方法について、下記のことに留意すべきである。
所得税法上、必要経費として認められるためには、青色申告者として取引記録等があり、その証憑書類が保存されていること及び業務の遂行上、必要なことが明らかなことである。
①青色申告者の帳簿
青
色
専
従
者 |
ケガの治療費 |
農作業を起因としたものならば必要経費
そうでない場合は家事費 |
| 衣服費 |
作業衣、作業靴は必要経費
下着や背広などは家事費 |
| 茶菓等の厚生費 |
社会通念上、一般使用人と同程度の常識的なものは必要経費
家族だけの旅行費用は家事費 |
| 研修費 |
農業に関係するものは必要経費
趣味など、農業に関係ないものは家事費 |
| 接待交際費 |
農業関係者との冠婚葬祭費は必要経費
親戚や友人とのお付き合いは家事費 |
| 運転免許取得費 |
大型特殊など特別・専門的なものは必要経費
その他は全て家事費 |
複式簿記でも簡易簿記でも、帳簿等に記帳されていることが必要である。複式簿記であれば総勘定元帳に記帳され、簡易簿記では経費帳や集計表があり、日付順・科目別に記録する。記帳方法は、事業分と家計分をその都度区分せずに総額を記帳し、後日の決算整理で区分処理をする。記帳のポイントは、家事関連科目でも全部事業用のこともあり得るので、そうでない場合とどのように区別するかである。パソコンであれば、1科目を事業専用と家事関連用の2つの小科目に分けた累計額の算出は容易であり、決算整理での仕訳も明確にできる。
②証憑書類の整理保存
スクラップブックに月別・日付別に、下から上に向かって貼り付ける。科目別に区別する必要は無いが、税金・保険料などの科目は後日の利便性を考えると専属ページが良い。当然、現金出納帳用と預金通帳用とは別冊にする。以上の区分整理で、日付順に記帳される現金出納帳の領収書は、スクラップブックに日付順に糊付け整理されることになる。
③必要性
スーパーでの茶菓や飲食料品等のレシートは、そのままのものが最善である。領収書に交換すると中身不明になり、後日の確認が不可能となり必要性にも疑
問が出てくる。同一スーパーでのレシートと領収書が混在している場合、帳簿の信用力を下げる懸念が生じる。レシートに事業用と家計用が混在して記載さ
れてもやむを得ない。事業用を○で囲むなどの工夫をし、その部分だけ記帳すること。家事関連費は必要性がポイントなので、その都度レシート等にメモをすることにより区分特定し、必要性を確保すること。
<事例:昭57.6.25奈良地方52(行ウ)6>
自宅の電話は、家族の日常的な使用を明らかに超えて大半が業務使用であるとは認められず、且つこれを区分特定することもできないので、自宅の電話代金
は必要経費にすることはできない。
④実務上の留意点
家事関連費は実際には面積、使用割合、業種別の標準数値、総務省の家計調査数値などを参考にして合理的に按分する。
2.本来は厳しい家事関連費
農業の青色決算書には「交際費」の科目が無いが、仕事に関連したものであれば必要経費として認められる。
参考までに、法人税では交際費等を次のように定義している。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。但し、従業員の慰安費用、カレンダーなどの物品贈与、会議費などは除く」。
上記のように、税法上の交際費の範囲は社会通念上の交際費より相当広くなっており、中小企業では年300万円超の部分は損金(税務上の必要経費)とならなかったが、平成18年度の税制で次のように改正されている。
①一人当たり5千円以下の一定の飲食費は損金となり、5千円以下か否かは、飲食等に支出した金額を参加人数で除して求める。
①社外の取引先等との飲食費が該当し、日付、支払先、金額、参加者名及び人数等を記載した書類の備置が必要である。有り難いことに法人と異なり、個人事業者には交際費の限度規定はなく、経費性があれば全額認められるが、家事費との区別が難しいことも事実である。
所得税では家事関連費の内、業務の遂行上直接必要であったことが明らかな部分は必要経費として認められるので、光熱費、自動車関連費用、減価償却費などのようなものは総額を事業関連割合で按分計算するのが通常である。
しかし、交際費等を前記の費用同様に按分計算することは適当でなく、オールorナッシングとなる。
農業経営との直接的な関連性の有無が必要経費になるかならないかの分かれ道になるので、具体的な証拠書類の整理保存が重要になる。
税務署とのトラブルを避けるための対策
①受領した領収書に、交際者の名前や人数及び話題等をメモしておく。
②安易に交際費科目で処理をしないで、会議費等の他の適切な科目で処理をする。
③専従者等の家族が同席している場合は、家事費にならないような充分な配慮をする。
原則: ①農業経営上、必要な支出であること
②金額は、通常必要と認められる程度
③取引先や従業員に対する冠婚葬祭費用であること
④親睦を主たる目的とした同業者グループの支出でないこと
⑤支出の実質により判断すること |
3.経営の法人化は黒字転換への第1歩
我が国の中小企業は、開業する者と倒産・廃業する者との両方を糾える縄のごとく発生させながら、20年間で約110万社減少している。一番多い原因は、競争の厳しさと収益性が低下する中で後継者がいなくなってしまった、ということである。
国税庁の統計数字によると、全申告法人の内、赤字企業が7割を占めている。つまり、赤字が長く続けば最後は廃業や倒産という状況に追い込まれ、その方が開業者よりも多いという、当たり前の現象が20年間も続いていることになる。それでは農業・農家はどうであろうか。確かに明治・大正・昭和の前半は、儲からなくても農家が廃業するなどということは殆どなかったようである。
しかし、経済がグローバル化している現代は違う。収益性が上がらなければ、子供は跡を継がず、代々続いてきた家業に終止符を打つことになる。資本主義の経済社会から競争は無くならないし、政治が競争をコントロールすることなど不可能であろう。
つまり、赤字経営ではなく、どうやって生産性を向上し黒字経営に転換するかが、産業として継続するための絶対条件である。そして黒字化を目標にした場合、農業経営の法人化は打ち手の一つになる。
国の政策は、認定農業者制度に見られるように、規模拡大と合理化を実現した企業的農業経営者の育成である。それ故、経営を法人化し、会計の精度を上げ、明確な目標を立てた経営を展開するPDCAは、黒字化を目指すことに非常に役立つ。
①Pはプラン、つまり目標たてること、
②Dはドウー、つまり目標に向かって行動すること、
③Cはチェック、つまり中途で検討すること、
④Aはアクト、つまり更なる改善行動を起こすこと。
この世の中に、「何となくやっていたら、儲かってしょうがない」というような人は、存在しない。例えばあなたが東京へ行こうという目標を立てたとき、電車、自動車、自転車、徒歩であっても、東京へ行くという明確な目標さえあれば、用いる手段の違いで時間差はあっても、いつかは必ず東京に着くことができる。
このことは計画や目標を立てることの重要さを意味しており、明確な目標を持つことは、われわれ凡人を成功に導く絶対条件である。よって、皆さんが作った農業経営改善計画書はPの段階だが、それがDにつながっているだろうか。自分の言葉で説明できる改善計画書になっているだろうか。5年かけて東京まで行くというような、行き先の明確な農業経営改善計画になっているだろうか。
経営を法人化することにより、早期に事業と家計を完全分離し、品目別損益計算を採用したり、数値目標を立て黒字化への挑戦をしなければ、あなたの農業経営者としての10年後の存続は危ない。だらしない帳簿のままで漫然と経営をしている経営者が淘汰されるのは歴史が証明している。逆に、本物の経営を展開するには、足下の帳簿をキチンとすることであり、その為には法人化が必要である。
| 法人化のメリット |
|---|
| ①会計を複式簿記で行うことにより、貸借対照表と損益計算書並びにキャッシュフロー計算書の作成を通じ、事業と家計の完全分離はもとより、適時適切な会計により黒字化を目指す経営を展開できる。 |
| ②法人格が取引の基礎になり、事業の継続に寄与し、対外的信用が高まる。 |
| ③少子高齢化の時代に入り、充分な労働条件を具備することにより、若手の雇用確保に寄与する。 |
| ④スーパーL資金を始め、長期低利の融資枠の大きい制度資金が借りられる。 |
| ⑤税制上、給与所得控除のメリットや交付金収入の圧縮記帳ができる。 |
| ⑥経営者同士のより盛んな交流機会が得られる。 |
| 法人化のデメリット |
|---|
| ①法人税の申告処理などのアウトソーシング費用が発生する。 |
| ②社会保険料の自己負担分が重荷になる。 |
| ③同族会社の課税強化対応が必要とされる。 |
|